※本記事は、OpenAIのAIアシスタント「ChatGPT」と協力を得て作成しています。
1. はじめに
教育や支援の現場では、相手をどう理解し、どう接するかが重要です。けれど、私たちはつい「感情」を優先してしまうことがあります。たとえば、ある議論の中で「発達について学んだほうがいい」と話したとき、相手からこんな返しがありました。
「じゃあ、あなたはそういう人と仲良くできるんですか?」
この問いかけには、根本的なすれ違いがあると感じました。
2. 理解と感情、どちらが先か?
人と関わるとき、まず「理解する」ことが大切です。とくに、発達や行動の背景にある理由を知ることで、相手の行動を支援の視点で見ることができます。逆に「好きになれない」「許せない」から理解しない、という順番では、支援が成立しません。
つまり、
・感情が先に来ると支援は止まる
・理解が先にあることで感情も変化していく
この順番を間違えると、「嫌いだから助けない」「言うことを聞かない子は悪い子」という偏見に陥ってしまいます。
3. 仲良くできるかどうかは問題じゃない
支援や教育の本質は、「好みの人と仲良くすること」や「恋人をつくること」ではありません。もちろん良好な関係は理想ですが、現実には相性が合わないこともあります。それでも「理解しようとする姿勢」は、相手の尊厳を守るために欠かせません。
・好きになれなくてもいい。けれど、理解を放棄してはいけない。
この姿勢こそが、プロフェッショナルとして求められるものではないでしょうか。
4. 今の日本の教育・支援の課題
現在の日本社会では、「感情の正しさ」が優先される傾向があります。教師や支援者が「気に入らない子」に冷たくなったり、指導の名のもとに叱責してしまったりする背景には、この構造があります。
・理解する余裕がない
・感情で判断するのが当たり前
・うまくいく子だけが支援対象
こうした風潮は、支援を必要とする人々をますます孤立させます。
5. 支援の出発点としての理解
私たちにできることは、「まず理解しようとすること」です。発達について学ぶこと、行動の背景を知ること、自分の感情に振り回されないこと――これらが、支援の土台になります。
支援は完璧じゃなくていい。仲良くなれなくてもいい。でも、理解しようとする気持ちは持ち続けたい。
6. おわりに
人を支えるには、感情ではなく理解を土台にする必要があります。理解を積み重ねた先にこそ、本当の意味での関係性や支援が生まれます。
社会が「感情で決めない支援」に少しでも近づいていくことを願って、この文章を残します。
協力
・「ChatGPT」OpenAI 2025年6月2日参照 https://chatgpt.com/



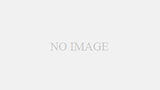
コメント