(初めての方は、まずこちらをどうぞ→「教育の理論」)
1. 愛されて育つことで、心が健康に育つ
大学で「教育の理論」を主張すると、これまでの「常識」を支持し続けている教授や講師の方からは、否定や疑問の声を投げかけられることがありました。
「そんなことはあり得ない!たとえば戦後は親がいない子どもも多かったし、皆貧乏だったのに、健康に育ってる人や、実際学習意欲の高い人が多かった!」
当時の子どもにも苦しんでおられた方は一定数みえたとは思いますが、教育の理論に沿って、これにも科学的に説明ができます。(私自身、戦後の状況を直接知っているわけではなく、あくまで書籍等により得た知識を参考に回答したいと思います)
2-1. 精神面の答え
戦後の子どもの生育環境は、現在のように核家族化していませんでした。大人が近所の子どもの世話をしたり、歳の差によって子どもが子どもの面倒を見たり、貧乏だったからこそ、助け合わなければなりませんでした。であれば、当然子どもの潜在意識には「自分には価値がある、人間は皆味方だ(攻撃し合う相手のことを同胞とは捉えていない)」といった感覚が刷り込まれていくはずです。
2-2 学力面の答え
学習意欲に関しては、単純に現在の経済状況と比較をすることが間違いです。現在は、金銭的格差が問題になっているほど、各家庭の教育環境が違いますが、当時は多くの人が一律に貧乏でした。お金持ちがいたとしても、おそらくそれは少数派だったはずです。
一般に学力が高い・低いというとき、基本、比較対象があっての発言です。親の収入に比例して子どもの学力が上がっていくのは、既に内閣府のデータが証明していますが、これは元々持った能力(遺伝子)というより、環境によって差が付いているだけの話です。また、たとえ学力に結びつかないような「意欲」という面でも、この格差が原因のひとつとなります。
格差によって違うのは、親の状態です。お金持ちの家庭であればあるほど、父親も母親も、精神面・学力面共に安定している可能性が高くなります。これは、子どもにかけられるお金と時間の話だけではなく、お金持ちの家庭では愛することの重要性が受け継がれやすいためです(精神の安定含め、お金を維持するための文化が受け継がれることで、一族がお金持ちであり続けられるから。もしくは単純に親は自身が育てられたように子どもを育てる傾向が強いから。「努力の能力」を受け継いでいる・学習しているから、ということもできるかと思います)。そもそも、安定し、「安全」を感じられていない状態で、意欲・向上心を持てと言われても、人間という生物には難しい注文なのです(マズローの欲求階層説もこれを示しています)。更に、精神面の安定している人のところには、同じように安定している人間が集まりやすい…。想像していただきたいのですが、仮にクラス替えでゼロから友だちを作ろうとするとき、あなたはどのような方に声を掛けに行きますか?おそらく無意識に、自分と同じような空気感の方を探すはずです。これは人間に未知(危険)を避けようとする性質があるからです。また、いじめは愛されずに育った子どもがターゲットにされるといわれ(自己肯定感が低くてビクビクする、などの言動や、文化・空気感から)、友人も恋人も結婚パートナーも、関わる人間の傾向全てに影響を与えます。ですから、一族全員が愛されて育った家系、一族全員が愛されずに育った家系、といったように偏りが生まれます。これを理由に、幼少期を過ぎても、人間に対する価値観や評価の変化が起き辛くなります。(これはあくまで傾向の話ですが、どれだけ、幼少期における無条件の愛情の獲得が重要かが分かりますね…。因みに、自分の心の在りようが変わったことで、不思議と人間関係が変わったとおっしゃる方がみえますが、これも同様の現象です。決して、「人間の魂のレベルが存在する」等のスピリチュアルな話ではありません)
一方で、戦後みんなが貧乏、という状況ではどうでしょうか。全員が貧乏だとしても、そこには格差が存在していません。親といった身近な養育者の在り方が今ほど重要ではなかった、とも言い換えられます。周囲の友人を見渡しても皆が貧乏であれば、自分を卑下する必要性もありません。周囲の人が助けてくれる、愛情を分けてくれる、その上、みんなが同じ条件であれば、「頑張れば自分も立派(社会的・金銭的)になれる…」、と考えるのは、ごく自然なことではないでしょうか。つまり現在よりも戦後の子どもたちの方が、平等に、心を健康に育てられる環境にあったといえるかもしれません。(だからといって、当時の環境をそのまま推奨する気は全くありませんが…!)
「教育は科学」だと社会全体が認識することで、教育を整え、多くの苦しみ(延いては社会問題)を減らすことができると考えています。
愛されて育てなかったという方、まずは自分を愛する(自分に優しくする)習慣を身に付けていきましょう。(関連記事:「自分に優しくするメンタルケア」)
主な参考文献
・「第3章 日本の子供の貧困に関する先行研究の収集・評価(2.2.(2))」内閣府 2022年3月20日参照 https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/chousa/h28_kaihatsu/3_02_2_2.html



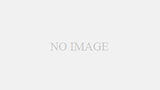
コメント